〒070-0832 北海道旭川市旭町2条15丁目 TEL:0166-51-8101 FAX:0166-51-8102 Mail:kyokumo-z0@hokkaido-c.ed.jp
サイトマップは「こちら」

〒070-0832 北海道旭川市旭町2条15丁目 TEL:0166-51-8101 FAX:0166-51-8102 Mail:kyokumo-z0@hokkaido-c.ed.jp
サイトマップは「こちら」
本日の放課後、校内研修が行われました。
今回のテーマは「点字の読み書きについて」です。
多くの先生方が参加して、点字について学び合いました。
点字の基礎を学んだ後に、それぞれの習熟度に応じた練習問題が出されたのですが・・・「ローマは一日にしてならず」ですね。
点字を少しは分かってきたと思っていたのですが・・・やはり日々点字に触れることが大切ですね。
この言葉でがんばります!
⠧⠐⠧⠀⠪⠛⠀⠈⠺⠒⠐⠳⠴ (日々是精進)

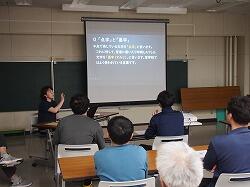
本日は小学部3年生の学習で、京都府立盲学校、愛媛県立松山盲学校、鹿児島県立鹿児島盲学校とをオンラインでむすんだ交流学習が行われました。
昨年度も「国語」や「算数」「道徳」などの授業で定期的に行われていた交流学習ではありますが、今年度としては最初のオンライン交流ということで、オリエンテーションも兼ねて、改めての自己紹介とクイズ大会で楽しみました。
画面を通してですが、私も昨年度から見ている、知っている子どもたちではありましたので、久しぶりに会えることを(拝見できることを)大変楽しみにしておりました。
みんな一つ学年が上がって、なんかお兄さんになっていましたね。・・子どもの成長は早いですね。
今年度も4校の交流学習がスタートいたします。
住む地域も、環境も違いますが、同じ小学3年生同士。同学年の友だちと学び合い、語り合い、笑い合い、たくさんのことを学んでいってほしいと思います。
京都、松山、鹿児島、そして旭川のみなさん、みなさんのこれからの成長を大変期待しております。
がんばってくださいね。


本日は寄宿舎で月に1回行われる「ランランタイム」の日。
みんなで体育館やグラウンドを走ります。
走った距離を毎回記録し、年度の終わりに総走行記録を発表し合い、みんなで讃え合う寄宿舎活動となります。
今年はみんなどれだけ走ることができるでしょうか。
アテネオリンピック・女子マラソン金メダリストの野口みずきさんはこう言っていましたよ。
「走った距離は裏切らない」
いい言葉ですね。そう、努力は裏切らないのです。
私も今年「旭川ハーフマラソン大会」に出場いたします。
舎生のみなさん、共にがんばりましょう!






本日も晴れの旭川。気温も昨日と同じ21℃予報となっており、暖かい一日となりそうです。
そんな陽気に誘われてか、幼稚部では学校近くの公園までお散歩とのこと。
いいですね~。
学校周りでも、大小様々な花が咲き始め、中庭のタンポポも今が盛りとなっております。
きっと公園でもたくさんの春に出会えるのでしょうね。
幼稚部のみなさん、たくさん春を見つけてきてくださいね。




本日は快晴の旭川。気温も22℃予報と暖かい一日となりそうです。
先週の木曜日、金曜日は全道の校長会ため学校を不在しておりましたので、久々の更新となります。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、本日の小学部3年生「理科」の授業では、「ほうせんか」の種まきが行われていました。
育苗ポットに種をまき、芽が出てきたら学校菜園に移植するとのこと。楽しみですね。
実は私(校長)も、お米の苗を育てております。
プラスティックの卵パックを活用し、種をまき発芽させました。
この苗も、この後、田んぼに植える予定となっております。
何かを「育てる」という経験は、多くの発見と気づきを与えてくれるもの。
また、「愛おしむ(いとおしむ)」気持ちも育ててくれますよね。
愛情をもって育てていきましょうね。




※先週まいた「ひまわり」の種から芽が出たそうです
旭川市の読み聞かせサークル『アウルの会』様にご協力をいただき、毎月1回、寄宿舎の余暇時間に絵本の読み聞かせ会を開いております。
本日(5/7)は今年度最初の読み聞かせ会ということで、5冊の本の読み聞かせをしていただきました。
みんなで笑い出してしまうようなおもしろいお話や、ラーメンとうどんの戦いのお話など、本日も楽しいひと時を過ごすことができました。
旭川市「アウルの会」のみなさま、本日はどうもありがとうございました。また、今年度もどうぞよろしくお願いいたします。


ゴールデンウィークも終わり、今日から学校再開。
子どもたちも元気に登校しております。
さて、5月は比較的落ち着いて様々な活動に取り組める時期ともなります。
来月6月には「運動会」も控えておりますので、その前に再度気持ちと身体を仕切り直して、学習に運動に落ち着て取り組んでほしいと思います。
ただ、気をつけなければいけないことが、春疲れ・・・いわゆる「五月病」というもの。
4月の慌ただしさと、ゴールデンウィークなどの連休を挟んだことで、普段のペースがつかめず、気持ちが持続しないことも。
あわてず、ゆっくり、一つ一つのことに着実に取り組んでいくことが大切になりますね。
5月のキーワードは『あわてず、ゆっくり、着実に』ですね。(自分にも言い聞かせて・・)








いつも学校ホームページ、並びに『校長徒然』をご覧いただきありがとうございます。
昨年4月からの累計で、視聴者数がなんと・・20万件を超えました。
たくさんの方にご覧いただき、本当にうれしく感じております。
今後も、旭川盲学校の今を、子どもたちの今をお伝えしてまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。
本日も快晴の旭川。暖かな春の日となっております。
明日からゴールデンウィークも後半戦となりますが、どうも天気は下り坂の模様・・・
今日のこの日ざしを存分に楽しみたいと思います。
さて、本校の子どもたちも、本日も元気いっぱい。
各教室から聞こえるにぎやかな子どもたちの声が、ここ校長室まで届いております。
人間がもつ感覚には、視覚以外、聴覚、嗅覚、触覚、味覚など、様々な感覚があります。
昨日、校内研修で行った「ゴールボール」もそうですが、視覚の情報がなくとも、聴覚や触覚を駆使し、ゲームを行うこともできます。
実は子どもたちの声からも様々な情報を得ることができ、目に見える様子よりも如実に心の内がわかることもあります。
人が春を認識するとき、もちろん雪が溶けた様子や木々が芽吹く様からも認識するのでしょうが、実は頬をなでる風であったり、土がぬるむ匂いであったり、鳥たちのさえずりや、ふきのとうの苦みであったり、様々な感覚を統合して春を感じているのでしょうね。
五感で感じる・・・大切なことかもしれませんね。










本日の放課後、パラスポーツをテーマに「ゴールボール」の校内研修が行われました。
特別講師として、本校卒業生のパラリンピアン、2008年北京パラリンピック出場の高田 朋枝さんにご来校いただき、ご指導をいただく機会に恵まれました。
高田さんは現在東京に在住で、ゴールボールの普及活動に励まれているそうですが、今回はちょうど旭川に帰省中ということもあり、特別に講師を引き受けていただけることとなりました。本当にありがとうございます。
ゴールボールとは、バレーボールほどのコートを使用し、3人一チームで鈴の入ったボールを投げ合い、ゴールを奪い合うゲームとなります。
もちろんチーム戦ですので、3人で連携してゴールを守るディフェンスもあり、ボールの投げ方にも細かなルールがあるなど、技術も経験も必要なスポーツとなります。
選手はアイシェード(目隠し)をして、視力や視野など障害の程度で差が出ないようにし、ボールから発せられる鈴の音だけを頼りに行われる競技となります。ですので競技中は本当に静かで、聴力だけが頼りとなります。
私も実際にプレーしてみたのですが、音を頼りに、ボールの動きをイメージして体を動かすため、高い集中力を必要とするスポーツであり、視覚の情報がない分、チーム内のコミュニケーションが非常に大切なことも分かりました。
その辺にこの競技のおもしろさと奥深さがあるように感じます。
大変貴重な学びでした。高田さん、本日は本当にありがとうございました。










本日は中学部で「新入生歓迎会」が行われ、寄宿舎でも、新舎生の「歓迎会」が行われました。
今日は歓迎会デーですね。
中学部の「新入生歓迎会」では、一人一人の自己紹介が行われた後に、歓迎のダンス、イントロクイズが行われました。
イントロクイズは難問・珍問ぞろいで、私は1曲も分からなかったのですが、さすがは生徒たち。
すかさず答えるあたりはさすがですね~。好きな曲では振りつけ付きで紹介もしてくれました。
寄宿舎の「歓迎会」では、舎室ごとの紹介の後に、お祝いの品のお菓子が全員に贈られました。
みなさんよかったですね。
今日で4月も終わり、明日からはいよいよ5月です。
年度のスタート、4月の最後の日に、みんなで盛り上がれてよかったですね!









現在、緊急の連絡はありません。
令和7年8月末現在の
いじめと思われる事案の件数は
「0」です。
▢北海道教育委員会
▢北海道立特別支援教育センター
▢道内の盲学校
▢たいせつネット
このホームページは、北海道旭川盲学校が教育利用を目的として運営している公式ホームページです。よって、内容、写真等の無断転載、営業誌掲載をお断りします。